
この記事の要約です♫
「リリックとは何か?」をテーマに、ラップ歴25年の可児波起が自身の体験を交えて解説。語源である古代ギリシャから現代の音楽ジャンルごとの使い方、プロの制作現場での実例、リリックを書くためのコツまで、初心者にもわかりやすく丁寧に紹介します。感情を言葉にする力、それを音楽に乗せる意味を伝える本記事は、「自分でもリリックを書いてみたい」と思っている方にぴったりのガイドです。
「リリック」って言葉、聞いたことありますか?
ラップやヒップホップの文脈でよく使われますが、実はポップスやロック、果ては詩の世界でも頻繁に登場する言葉です。
でも、いざ「リリックって何?」と聞かれると、
「歌詞のことじゃないの?」とか
「なんとなくカッコいい言い方でしょ?」
そんな曖昧な印象を持っている方も多いかもしれません。
僕は、25年にわたって音楽活動を続けているラッパー・歌い手で、メジャーデビューも経験している「可児波起(かになみき)」という名前で活動しています。
グループ「STAND WAVE」では“ネイチャーヒップホップ”という独自ジャンルを築き、自然や命、人とのつながりをテーマに、たくさんの“リリック”を書いてきました。
リリックは単なる「歌詞」ではありません。
それは、心を震わせ、人生を変えるほどの“言葉の力”を秘めています。
この記事では、「リリックとは何か?」という言葉の意味や使い方を、プロの音楽家としての僕の視点から、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
第一部では、「リリック」という言葉の語源と意味を解き明かし、
第二部では、音楽ジャンルごとに異なるリリックの使われ方、
第三部では、実際に僕が書いたリリックの例や制作エピソードを紹介しながら、言葉の持つチカラとその使い方について深く掘り下げていきます。
この記事を読み終えたころには、「リリック」という言葉に対する理解が深まるだけでなく、自分でも何かを“書きたくなる”ような、そんなインスピレーションを感じていただけるはずです。
ではまず、第一部から一緒に読み進めていきましょう。
「リリックとは?」——その言葉に込められた意味の旅へ、ようこそ。
第一部:リリックとは何か?言葉の意味と語源を深掘りする
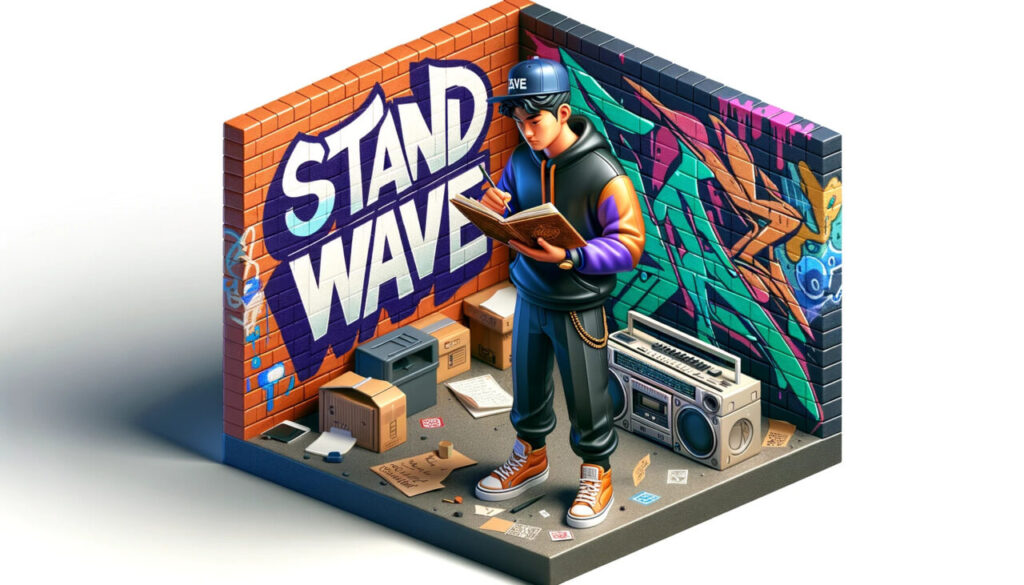
リリック=歌詞?それだけじゃ語れない“言葉の世界”
「リリック(Lyric)」という言葉は、日本では「歌詞」や「ラップの言葉」として広く知られるようになりました。
でも実は、リリックにはもっと深くて広い意味があります。
ラッパーとして活動している僕も、最初の頃は「リリック=ラップの歌詞」くらいの感覚でした。
でも25年も音楽と向き合ってきた中で、リリックはただの“文字”ではなく、感情や物語、魂を運ぶ“言葉の刃”のような存在だと感じるようになりました。
では、この「リリック」という言葉、どこから来て、どんな背景を持っているのでしょうか?
リリックの語源は古代ギリシャにあった
「リリック(Lyric)」の語源は、実は古代ギリシャ語の「lyrikos(リュリコス)」に由来しています。
この言葉は「リラ(Lyre)」という弦楽器を伴奏にして詩を歌う表現から生まれました。
つまり、もともと「リリック」とは、“楽器とともに歌われる詩”という意味だったんです。
当時の詩人たちは、単に文字を読むのではなく、感情を込めて声に出し、音楽と一体化して人の心に届けていたわけです。
ここには、現在のラッパーやシンガーが持つ表現の原点があると僕は思っています。
英語の「Lyric」は詩的な言葉や感情表現を意味する
現代英語での「Lyric」という言葉には、以下のような意味があります。
- 音楽の「歌詞」
- 詩的な表現、感情に満ちた言葉
- 短い詩の形式(=リリック・ポエム)
つまり、単なる“歌の言葉”にとどまらず、「感情を乗せて書かれた詩」というニュアンスが含まれているんですね。
たとえば、エド・シーラン(Ed Sheeran)のラブソングや、テイラー・スウィフト(Taylor Swift)の内省的な楽曲も、感情表現が豊かで“リリック的”と言えます。
リリックはジャンルを問わず、心を伝えるための「言葉のアート」なんです。
日本で「リリック」という言葉が広まったきっかけ
日本で「リリック」という言葉がポピュラーになったのは、ヒップホップ文化の広まりがきっかけです。
1980年代〜1990年代の日本では、ZeebraさんやK DUB SHINEさん、Rhymester(ライムスター)といったラッパーたちが、ラップ文化を日本に定着させていきました。
彼らは、「歌詞」ではなく「リリック」という言葉を使い、言葉の持つリアルなチカラや、社会的なメッセージ性を強く打ち出していたんです。
僕が活動を始めた1998年も、まさにそうした文化が根付いてきた時代でした。
当時使っていたのは、「AKAI MPC 2000 XL」や「Roland TR-808」、KORGの「TRITON」など。
そんなハードウェアと格闘しながら、言葉をビートに刻んでいく。まさに“言葉が命”の音楽でした。
そしてその中で僕も、「歌詞」ではなく「リリック」と呼ぶことで、単なる言葉ではなく“生き様や思い”を込めるようになっていったんです。
リリックには「生き方」が宿る
「リリック」とは、単にメロディに乗せる文字ではありません。
むしろその逆で、リリックこそがメロディやビートを動かす“エンジン”になることもあります。
僕自身、介護職をしながら音楽活動をしていた時期に作った曲「幸せの歌」では、リリックの1行1行が、実際の介護現場で感じた気持ちや、出会った人たちの人生をそのまま写し取ったものでした。
その曲は、朝日新聞財団の復興支援プロジェクトに採用され、被災地でも多く歌われるようになりました。
あれは、リリックが人の心と社会を動かした瞬間だったと思います。
第一部まとめ:「リリック」は心を運ぶ言葉
リリックとは、古代ギリシャに端を発する「感情を音楽に乗せて伝える詩」であり、
現代ではラップや歌の世界において、心の叫びやメッセージを届ける“言葉のチカラ”として息づいています。
それはただの「歌詞」ではなく、時に人生そのものを語る“詩”であり、“生き様”でもある。
音楽のジャンルを問わず、誰もがリリックを書けるし、感じられる。
次の第二部では、ジャンルごとに「リリック」がどう使われているか、そしてどう違うのかを具体的に見ていきます。
ラップ、ポップス、ロック、R&B……それぞれのスタイルに宿るリリックの魅力に迫っていきましょう。
第二部:ジャンル別に見るリリックの使われ方と特徴
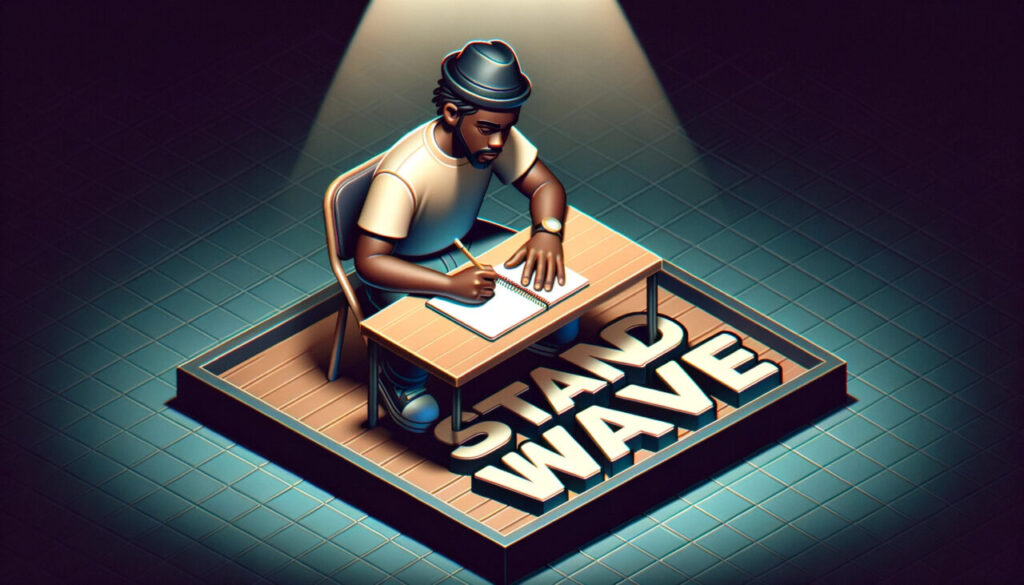
音楽ジャンルによって変わるリリックの姿
リリックは、どのジャンルの音楽でも“言葉を届ける”ための大切な要素です。
でも、ジャンルによってそのアプローチや魅せ方には違いがあります。
僕は25年以上、ラップ・ヒップホップを軸に音楽を作ってきましたが、ポップスやロック、R&Bなどの世界にも数多く触れてきましたし、実際にそういったジャンルへの楽曲提供もしてきました。
この章では、ジャンル別に「リリック」の使われ方や表現の違いを、プロの目線からわかりやすく解説していきます。
ラップ・ヒップホップにおけるリリックの役割:魂のドキュメンタリー
ラップの世界において、リリックはまさに“命そのもの”です。
メロディよりも先に、言葉が先行するジャンルとも言えるでしょう。
ラッパーは、自分の過去や社会への想い、人間関係、時に怒りや悲しみを、リリックで包み隠さず表現します。
僕が「介護ラッパー」としてフジテレビで紹介されたときも、
実際の介護現場で起きた出来事や、命と向き合う中で感じた想いを、そのままリリックにして届けました。
ヒップホップは元々、社会の中で声を上げにくい人たちの「叫び」や「日常」をビートに乗せて表現するカルチャーです。
だからこそ、リリックにはリアリティとメッセージが求められるんです。
たとえば、NASの『N.Y. State of Mind』、2PACの『Changes』のような名曲には、
言葉だけで社会を動かせる力があります。
それこそが、リリックの真骨頂です。
ポップスにおけるリリック:共感とメロディのハーモニー
一方で、J-POPや洋楽ポップスにおけるリリックは、
リスナーの“共感”を呼ぶ言葉としての役割が大きくなります。
たとえば、back numberの『ハッピーエンド』、米津玄師さんの『Lemon』、Aimerの『残響散歌』など、
誰もが感じたことのある「別れ」「憧れ」「希望」「苦しみ」といった感情が、抽象的なようでとてもリアルに描かれています。
ポップスのリリックは、
“言葉そのものの響き”や“メロディとの相性”も意識して練られていることが多いんです。
僕が提供した映画用の楽曲『記憶の中の青い春』も、
青春の一瞬を切り取るようなリリックを意識して書きました。
一人ひとりの“思い出”にそっと寄り添える言葉、それがポップスリリックの魅力ですね。
ロックにおけるリリック:反骨・内省・哲学の詩
ロックにおけるリリックは、ヒップホップ同様、メッセージ性が強いことが特徴です。
例えば、Nirvanaのカート・コバーンが書くリリックには、社会への不満や自己否定、
だけど同時に「真実を知りたい」という強烈な欲求が込められています。
日本でも、THE BLUE HEARTSの『青空』や、RADWIMPSの『おしゃかしゃま』のような楽曲には、
心の奥をえぐるような“哲学的リリック”が存在します。
ロックのリリックは、感情を爆発させるような勢いと、どこか文学的な深みを持ち合わせています。
まるで叫ぶ詩人たちが書く“魂の小説”のように。
僕も過去に、「苺の苗」という楽曲で、
環境問題や人間の欲望について内省的なリリックをロック寄りのサウンドに乗せて表現したことがあります。
ラップとは違う“情熱の言葉”を感じた瞬間でした。
R&Bにおけるリリック:感情を流れるように伝える言葉
R&Bでは、リリックは「感情の水流」のようなものです。
声の表情と一体になって、愛、別れ、孤独、希望を柔らかく描きます。
たとえば、アリシア・キーズ(Alicia Keys)やジョン・レジェンド(John Legend)の曲を聴くと、
一語一語が感情に寄り添うように流れてきますよね。
僕のグループ「STAND WAVE」では、「優しくありたい」という楽曲で、
“争いよりも共感を”というメッセージをR&Bスタイルのトラックにのせて届けました。
リリックはとてもシンプルに、でも確かに心に届くように──そんな意識を持って書いた言葉たちです。
ジャンルを超えて、リリックは“自分の声”になる
リリックという言葉には、ジャンルを超えた普遍性があります。
どんな音楽であれ、そこに“誰かの心”があるなら、それはリリックとしての価値を持つんです。
ラップでは、現実と向き合いながら叫ぶ。
ポップスでは、そっと背中を押す。
ロックでは、世界に問いかける。
R&Bでは、優しく寄り添う。
音楽の形が変わっても、リリックの本質は「誰かに何かを伝えること」。
そしてそれは、言葉を綴る“あなた自身”の声でもあります。
第三部:プロの現場から見たリリック制作のリアルとコツ

リリック制作は「感情」と「構造」のバランス
リリックを書くとき、僕が一番大事にしているのは「感情のリアルさ」です。
でもそれだけでは、曲として成立しない。
だからもうひとつ大事なのが「構造」です。
リリックって、感情を自由にぶつければ良いと思われがちですが、
実は“伝えるための設計”が必要です。
たとえば、感動する映画や本にも起承転結がありますよね。
同じように、リリックにも「導入」「展開」「フック(サビ)」「結び」のような流れがあります。
僕がCubaseを使ってトラックに言葉を乗せるときも、
その流れを意識しながら「どのタイミングでどんな感情を届けるか」を考えています。
リリックは“フック”が命:心に残る1行をどう作るか
ラップやポップス、ジャンルに関わらず、
リスナーの心に一番残るのは「フック(サビ)」です。
そこにどんな言葉を使うかが、楽曲全体の印象を左右します。
だから僕は、サビに使うリリックは1行1行、何度も書き直します。
たとえば、僕の代表曲のひとつ『大樹』のサビには、
「何も語らず ただそこに立ってた」
という一行があります。
このフレーズは、実際に僕が山の中で古い大樹と出会ったときに感じた、
“言葉じゃない存在の強さ”を表現したものです。
この一行が生まれるまでに、ノート10ページ分の言葉を書き殴って削ぎ落としました。
リリックとは、時に“削る芸術”でもあるんです。
日常がリリックの宝庫:アイデアの拾い方
よく聞かれるのが、「どうやってリリックのネタを見つけるのか?」という質問です。
僕の答えはシンプルで、「日常に全部ある」です。
たとえば、
・介護の仕事で見た“最期の笑顔”
・電車で見かけた親子の会話
・夜の帰り道にふと思い出した子どもの頃の夢
そういう何気ない瞬間が、実は最もリアルで心に響く言葉になります。
たとえば、僕が書いた『給水塔』という曲は、
子どものころ見ていた風景と、大人になって変わっていく町を重ねたリリックから生まれました。
「昔の空は高かった あの塔の先に未来を見た」
こんな一行が書けるのは、実際にその風景を“生きてきた”からだと思っています。
書けない時期もある。それでも“声”を探し続ける
正直に言うと、リリックがまったく書けない時期もあります。
言葉が出てこない。感情も乗らない。音楽に向き合うのが怖い。
そんな時は、僕も何度もありました。
でも、不思議なもので、ある日ふとした瞬間に1行だけ降りてくるんです。
僕が『幸せの歌』を書いたときもそうでした。
介護の現場で、重度障がいのある方が「ありがとう」と微笑んだとき、
涙が出るほど嬉しくて、その感情をメモ帳にそのまま書きました。
「幸せって何ですか?と問いかけたら あなたが笑って答えてくれた」
この一行から、丸ごと1曲が生まれたんです。
だからこそ、僕はいつでも“心のノート”を開いておくようにしています。
スマホのメモ帳、ボイスメモ、手書きのノート、何でも使います。
大事なのは、書こうとすることじゃなく、“感じようとすること”。
リリックは「誰かの物語」にもなれる
最後に僕が一番大切にしていることをお話します。
リリックは、最初は“自分の物語”から始まります。
でも、誰かがその曲を聴いたとき、それが“その人の物語”にもなるんです。
たとえば、僕の曲を聴いて「泣いた」「元気が出た」「背中を押された」と言ってくれた人が何人もいます。
そういう声をもらうたびに、「リリックって、人と人をつなぐ橋になるんだ」と実感します。
だからこそ、これからも僕は“本当の気持ち”を、リリックに込めていきたいと思っています。
飾らない、嘘のない、自分の言葉で。
よくある質問:リリックに関する疑問にプロが答えます

Q1:リリックと歌詞ってどう違うんですか?
A:意味は似ていますが、ニュアンスが少し違います。
「リリック」は、英語で“感情を込めた詩”という意味があり、特にラップやヒップホップでは、自分の思いやメッセージを込めた“表現としての言葉”という意味合いが強いです。
一方、「歌詞」はもう少し広い意味で、メロディに乗せて歌う言葉全般を指します。
つまり、すべてのリリックは歌詞かもしれませんが、すべての歌詞がリリックとは限らないというイメージです。
僕自身は、心からの想いやストーリーを伝えるときは「リリック」、
軽やかに歌いたいポップな曲のときは「歌詞」と呼び分けることもあります。
Q2:初心者でもリリックは書けますか?
A:もちろん書けます!むしろ初心者の方が、素直でリアルな言葉が書けることも多いです。
リリックを書くのに、特別な資格や知識は必要ありません。
必要なのは、「自分の気持ちを言葉にしたい」という気持ちだけです。
最初は難しく感じるかもしれませんが、
好きな曲のリリックを写してみたり、自分の日常を短く書いてみるだけでも十分な練習になります。
僕も最初の頃は、B5ノートに毎日10行の言葉を書き続けていました。
そうやって書いているうちに、自然と“自分の声”が見えてくるはずです。
Q3:いいリリックを書くにはどうすればいいですか?
A:たくさん書くことと、たくさん感じることです。
いいリリックを書くコツは、“人に届く言葉”を使うことです。
難しい言葉やテクニックを使わなくても、
たった1行で人の心に響くことがあります。
たとえば、僕の楽曲『one day』では、
「今日じゃなくてもいい でも明日には届くと信じてる」
というリリックが、多くの人に「励まされた」と言ってもらえました。
誰かに届けたい想いがあるなら、それはすでに“リリック”の種です。
あとは、その想いを言葉にするだけ。
そして、書いたら人に読んでもらう、聴いてもらう。それが何よりの成長になります。
Q4:リリックを書くときに参考にすべきアーティストはいますか?
A:たくさんいますが、ジャンルや好みに合わせて選ぶと良いです。
たとえば…
- ラップなら:2PAC、NAS、Zeebra、KREVA
- ポップスなら:米津玄師、Aimer、back number
- ロックなら:THE BLUE HEARTS、RADWIMPS、BUMP OF CHICKEN
- R&Bなら:Alicia Keys、清水翔太、宇多田ヒカル
それぞれがまったく違う表現方法で「言葉」を使っています。
ぜひいろいろなアーティストのリリックを読み比べてみてください。
ちなみに僕は、初期の頃はEminemやLauryn Hillのリリックに衝撃を受けて、
そこから自分でも「こう書いてみたい」と思うようになりました。
Q5:自分で書いたリリックに自信が持てません…。
A:最初から完璧なリリックなんて、誰も書けません。
リリックは、何度も書いて、削って、練り直すものです。
むしろ、書き直しているうちに「これが自分の伝えたい言葉だ!」という感覚が見つかってきます。
僕の代表曲『優しくありたい』のリリックも、完成までに10回以上書き直しました。
それでも、最終的に「この言葉で良かった」と思えたからこそ、届けられたと思っています。
だから、迷ったり悩んだりするのも大切なプロセスです。
焦らず、自分のペースで、言葉を育てていきましょう。
まとめと感想:リリックとは、自分の心を世界とつなぐ“言葉の橋”
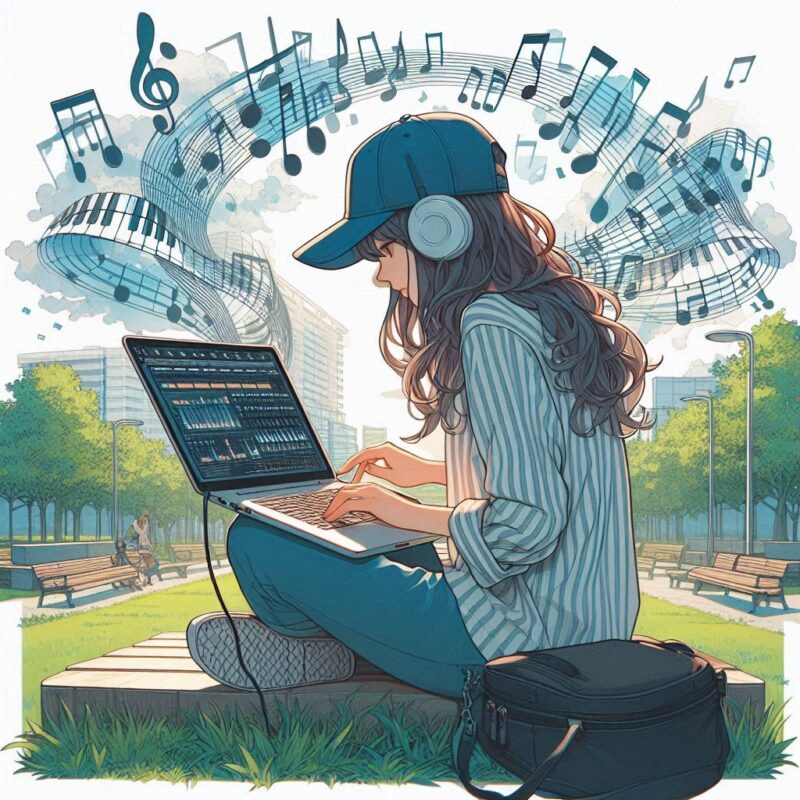
ここまで、「リリックとは何か?」というテーマを通じて、
言葉の意味、使い方、ジャンルごとの違い、そして僕自身の経験や制作エピソードをお話ししてきました。
この記事を読み進めてくださった方の中には、
「リリックってもっと深い意味があったんだ」
「自分でも書いてみたい」
そう感じてくれた方もいるかもしれません。
嬉しいです。
僕にとって、リリックとは“自分の生きた証”みたいなものです。
1998年、まだDAWも手に入らず、AKAI MPC 2000 XLやTR-808を駆使していた頃から、
僕はずっと「言葉」に救われてきました。
介護の仕事をしながら、夜にこっそりノートを開き、
自分でもどうにもならない気持ちをひとつひとつリリックに書いていく──
それは、音楽としての表現であると同時に、自分を保つための“祈り”のような時間でもありました。
たとえ誰かに聞かれなくても、
その1行が本物であれば、いつかきっと届く。
そう信じて書き続けてきました。
そして今、リリックという言葉に興味を持ち、
このブログを読んでくれているあなたの存在が、
僕にとっては何よりの“答え”です。
これから、リリックを書いてみたいと思っている方へ──
難しく考えすぎず、あなた自身のことをあなたの言葉で綴ってみてください。
それが誰かにとっての「共感」や「希望」になるかもしれません。
音楽の形は変わっても、言葉の力は変わらない。
そして、リリックというのはまさに“その力”を信じて書かれるものだと、僕は思っています。
これからも、自分のリリックを大切にしながら、
誰かの心に寄り添える曲を作り続けていきたい。
そう心から感じています。
──読んでくださって、本当にありがとうございました。
また、どこかの言葉の交差点で会いましょう。
リリックという橋の向こうで。
可児波起(かになみき)
STAND WAVE






